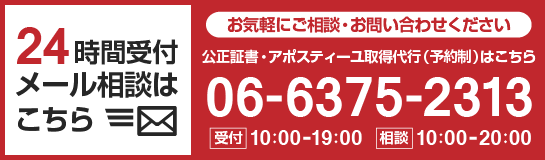遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、複数の相続人がいる場合に、被相続人(亡くなった方)の遺産をどのように分けるかを話し合い(=協議)で決め、その内容を書面にしたものです。
日本の民法では、法定相続分が定められていますが、実際の相続手続では「誰がどの財産を受け取るのか」を明確にする必要があります。そのため、相続人全員の合意に基づく文書=遺産分割協議書が不可欠になります。
不動産の名義変更、銀行口座の解約、株式や自動車などの名義変更等の手続きには、相続人全員の署名・押印済みの遺産分割協議書が求められます。
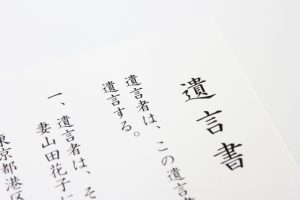
遺産分割協議書の内容の基本構成
①被相続人の氏名、死亡日、最後の住所
②相続人全員の氏名・続柄・住所
③相続財産の内訳と分配内容(不動産、預貯金、証券など)
④誰が何を相続するか
⑤相続人全員の署名・実印による押印
⑥各自の印鑑証明書の添付

遺産分割協議書の有効性の条件
①相続人全員が参加して合意していること(1人でも欠けると無効)
②実印での押印と、印鑑証明書の添付
③遺産分割協議書は法的に強制力のある契約書として扱われます(ただし公正証書ではない)

遺産分割協議書作成の際の 注意点
①遺言書がある場合は、その内容が優先されます(ただし相続人全員の同意があれば遺産分割協議を行うことも可能です)
②海外に相続人がいる場合、署名証明、公証、翻訳、アポスティーユなどの追加手続が必要になります
海外に相続人がいたり、遺産分割協議書を海外の役所・金融機関などに提出する必要がある場合、“アポスティーユ(apostille)”の取得が重要になります。アポスティーユは1961年のハーグ条約に基づく証明書で、日本の外務省または一部の公証役場が公文書の真正さを国際的に保証します。ただし、どの場面で必要か、取得方法やコストはどうかなど、適切に理解して準備しないとトラブルや手続きの遅延につながります。

アポスティーユとは?
アポスティーユ(Apostille)は、1961年に制定された“公文書の認証に関するハーグ条約”に基づく付加証明書です。これは条約加盟国間では、公文書を再認証なしに利用できる仕組みで、日本も1999年に加盟しています。アポスティーユは原本に貼付され、“この文書は正真正銘のものである”と他国政府に対して認めるためのものです。
必要な書類は遺産分割協議書だけでなく、戸籍謄本、住民票、署名証明など幅広く対象です。これらの書類は、日本国内の役所発行のものだけでなく、公証人による翻訳後にもアポスティーユが付与可能です。

遺産分割協議書の翻訳公証・アポスティーユが必要となるケース
では、遺産分割協議書にアポスティーユが必要となるケースは、主に、海外在住の相続人が遺産分割協議に関与する場合です。
海外在住の相続人は日本の印鑑登録証明が取得できません。そのため大使館・領事館もしくは所在地国の公証人(Notary Public)による「署名証明(サイン証明)」が必要になります。
この署名証明付きの遺産分割協議書を海外の機関(海外の不動産登記所・証券会社・銀行など)に提出する際は、協議書の真正性を保証するアポスティーユが求められることがあります。

遺産分割協議書の翻訳公証・アポスティーユ認証を行う場合の注意点
遺産分割協議書の翻訳公証・アポスティーユ認証を行う場合の注意点は次の通りです。
①提出先国の確認
→提出先がハーグ条約加盟国でなければ、原則的に外務省のアポスティーユではなく外務省の「公印確認」+領事認証が必要です。
。
②証明書の有効期限
→アポスティーユ付き署名証明書は3ヶ月~6ヶ月有効と見なされることがあり、金融機関や登記所はそれに準じます 。
③認証方式の違い
→後に協議書に署名・割印を受ける場合と、別紙方式(署名を別紙に署名し割印)があります。手続先に確認が必要です 。
④翻訳品質が悪いと受理されないことがある
→遺産分割協議書は相続財産に関わる協議内容をまとめたもので、法的に厳格な内容なので、翻訳品質が悪いと受理されないことがあります。
そのため、法務翻訳に実績のある翻訳事務所に依頼すると安心です。
。

まとめ
海外関連の相続手続きは、提出先国の要件を事前によく確認し、公証・アポスティーユ・署名証明など必要証明を一括取得する体制が重要です。専門の行政書士や法律翻訳事務所と連携することで、手続きの抜け漏れ、提出遅延、再申請などのリスクを軽減できます。
当事務所では、10年以上にわたり、遺産分割協議書の翻訳公証・アポスティーユ認証を行ってきておりますので、お困りの場合は、専門家によるサポートをご検討ください。
お見積もりフォーム